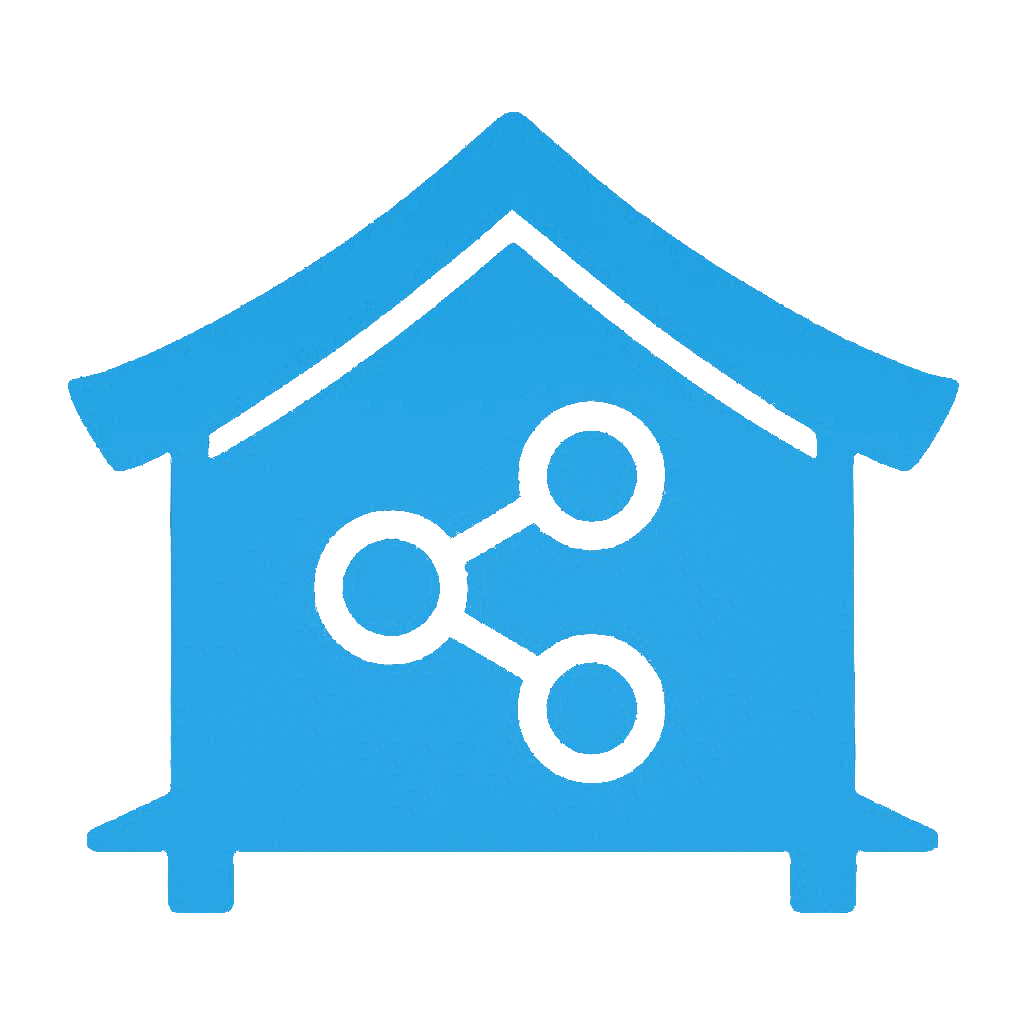💡 スマートライトを「触らずに」使えるようになるまでの話
Amazonのアソシエイトとして、Smart Home Laboは適格販売により収入を得ています。
2014年、私は初めてスマートライトを手に入れました。 それが Philips Hue スターターキット(ハブ+RGBW電球3個セット、 こんな感じの製品 )です。
スマホから電気をつけたり、色を変えたりできる―― まるでSF映画の未来の家に住んでいる気分でした。 その日、友人を呼んでライトの色を変えながら「見て見て、青にできるんだ!」と自慢したことを今でも覚えています。
でも1ヶ月もすると、その未来感は少しずつ面倒になってきました。 スマホを取り出す → ロックを解除 → アプリを開く → ライトを操作する。 この一連の動作が、特に夜中や寝起きのときはとても億劫で、普通の壁スイッチの方がずっと早いことに気づいてしまったのです。
🧠 リモコンという原点回帰
Section titled “🧠 リモコンという原点回帰”そこで次に手を出したのは、安いスマート電球とリモコンのセットでした。 この選択が意外なほど便利で、Philips Hue よりもずっと頻繁に使うようになりました。
ここで私は、あることに気づきました。
「スマート」とは、最新技術を意味するのではない。 **“手間がかからないこと”**こそが本当のスマートなのかもしれない。
リモコンを手に持った瞬間、ライト操作はほとんど自動的に、無意識に行われるようになりました。 夜中にトイレに行くときも、手探りでスイッチを探す必要はありません。 小さなリモコン一つで、生活がぐっと快適になった瞬間でした。
🎙️ 初めての音声操作
Section titled “🎙️ 初めての音声操作”その後、「SARAH」というオープンソースの音声操作プロジェクトを見つけました。 対応しているスマートライトは限られていましたが、自分でコードを追加して対応させることに成功。
当時はそんな自己満足感に浸っていました。 (ちなみに、Amazon Alexa が日本で発売されたのは2017年末です。先取りしすぎてちょっと寂しい時代感…)
しかしここでも、またしても同じ壁にぶつかります。 音声認識の失敗や、デバイス名を忘れてしまうことが続き、徐々に使わなくなってしまいました。 結局、手元にあるリモコンや物理スイッチの便利さには敵わなかったのです。
🚪「操作しなくていい」照明へ
Section titled “🚪「操作しなくていい」照明へ”時が経つにつれ、私の考え方は変わりました。 「どう操作するか」よりも、**「操作しなくてもいい仕組み」**こそが重要だと気づいたのです。
そこで手を出したのは、センサーを使った自動化です。
- クローゼットにはドアセンサーを設置 → 開けると点灯、閉めると消灯
- トイレや廊下、脱衣所には人感センサーを設置 → 通ると点灯し、しばらくして自動で消灯
Home Assistant には便利な モーションライト用のブループリントもあります👇
さらに、パターンが読めない部屋や、特定の動作に合わせた照明には、スマートスイッチを導入しました。 スマホも声も不要、物理ボタン一つで完結するこの安心感は、まさに「スマートとはこういうことか」と実感させてくれました。
🪄 お気に入りのスマートスイッチ
Section titled “🪄 お気に入りのスマートスイッチ”賃貸暮らしなので壁スイッチの交換はできません。 そこで 既存スイッチの横に貼り付けるタイプ のスマートスイッチを導入しました。 古いスイッチは このカバー で封印。見た目もすっきりです。
今では、家の中のあちこちにスマートスイッチを配置しています:
- ソファの横
- デスクの上
- ベッドのそば
これらは単にライトをつけるだけでなく、掃除機の起動やカーテンの開閉まで操作可能。 特にお気に入りは次の2つ👇
ボタンごとに「短押し・長押し・ダブルタップ」を設定できるので、小さなパネル一つで家全体を操るような感覚に。 これはもう、魔法のスイッチです。
📍 外出中でも自動で消灯
Section titled “📍 外出中でも自動で消灯”さらに便利なのは、 Home Assistant Companion アプリ ( iOSはこちら )の位置情報連携。
家を出ると自動でライトがオフになり、帰宅すると玄関の照明がそっと点く。 もう手動でスイッチを操作する必要はありません。 家が自分の動きを読み取り、自然に寄り添ってくれる感覚――まさに「触らずに使える照明」です。
💡 電球の選び方
Section titled “💡 電球の選び方”長年の試行錯誤で、電球は大きく3タイプに分けられると感じました👇
| 種類 | 特徴 | おすすめ度 |
|---|---|---|
| オン/オフのみ | 明るさ・色温度を変えられない | 正直おすすめしません |
| 可変ホワイト(白色温度調整) | 昼はクール、夜はウォームな光に | メイン照明に最適! |
| フルカラー(RGB) | ムードライトやアクセント用 | 補助照明におすすめ |
特に可変ホワイトは、生活リズムに寄り添う光を作れるのが魅力です。 朝の目覚めに少しクールな光を、夜のリラックスタイムには暖かい光を―― 光一つで1日のメリハリをサポートしてくれる存在になりました。
🌅 さらに自然な照明へ:Adaptive Lighting
Section titled “🌅 さらに自然な照明へ:Adaptive Lighting”そして最後のステップは、HACS(Home Assistant Community Store)から導入できる Adaptive Lighting です。
時間帯に応じて自動で色温度と明るさを調整してくれるこの仕組みは、まさに生活のパートナー。
- 朝は明るくクールに ☀️
- 昼は自然でバランスよく 🌤️
- 夜は暖かく穏やかに 🌙
設定したら放っておくだけで、1日中「ちょうどいい光」が維持されます。 手動で操作する必要はもうほとんどありません。 まさに理想のスマート照明です。
🏡 おわりに
Section titled “🏡 おわりに”2014年の私は、「スマート」とは“自分でコントロールできること”だと思っていました。 しかし今は違います。
本当にスマートなのは、何もしなくてもいいこと。 スマホも、声も、スイッチさえも必要ない。 家が自分の生活パターンを理解し、自然に寄り添う―― そんな照明こそ、真の「スマートライティング」です。
ちなみに――あの2014年に買った Philips Hue の電球、 今でも実家で元気に光っています。 長い旅を経て進化してきたのは、私だけでなく、家の光も同じなのだと感じます。